ジョン・カサヴェテス・レトロスペクティブ
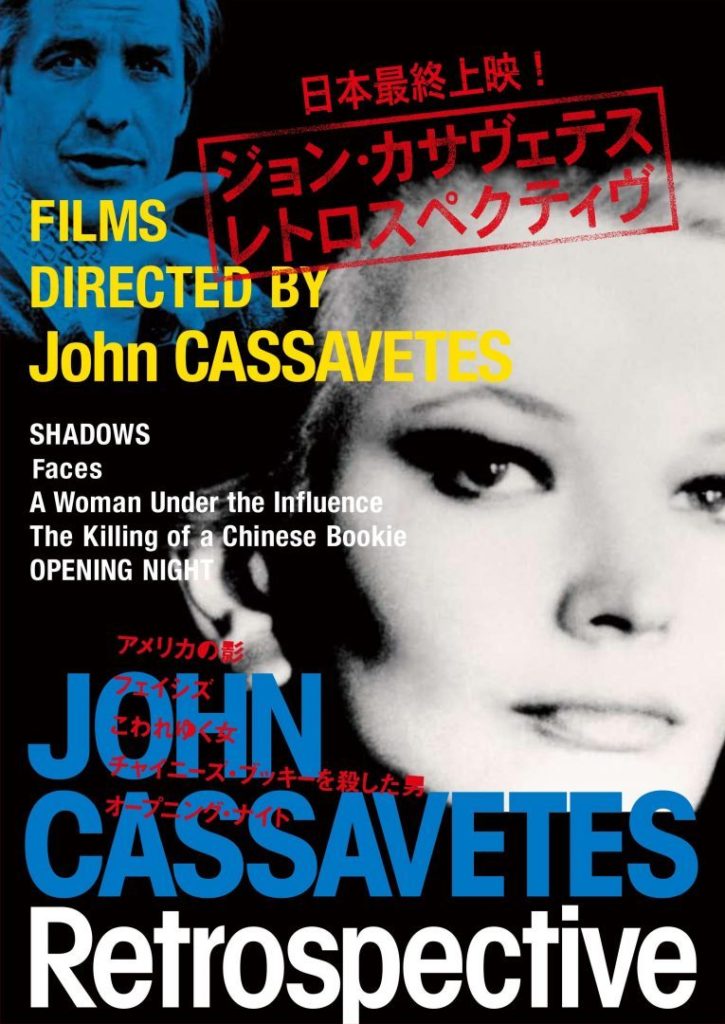
アップリンク渋谷で「ジョン・カサヴェテス レトロスペクティブ」を見る。上映権が切れて日本の最終上映になるというので、見逃していた作品を土日にまとめて鑑賞。カサヴェテス作品を1日三本立てで見るなんて疲れそう・・・と思ったんだけど、ここしか時間が取れなかったので無理矢理押し込む。でも、やっぱりつらいものがありました。いい歳だからそろそろこういうバカな真似はやめた方が良いよな、と反省。
カサヴェテスについては、いまさら説明する必要もないだろう。俳優から監督に転じ、1959年の「アメリカの影」でデビュー。即興演出と長回しでニューヨークを舞台にした作品を撮り続け、インディペンデント映画の新たなスタイルを確立した。妻のジーナ・ローランズは、彼の多くの作品に出演している。僕らの世代は、商業的にも成功した「グロリア」ではじめてカサヴェテス作品に触れ、「ラブ・ストリームス」や「オープニング・ナイト」を見て彼の作品世界に入っていった。80年代ミニシアターで脚光を浴びた「巨匠」のひとりである。
僕は、個人的にはカサヴェテスの作品はあまり好きではない。彼以外の誰にも撮れないスタイル、即興演出とは言え、人間の心の深層までを描き出してしまう作品世界。狂気すれすれまで追い詰められた人間の精神を体現してしまうジーナ・ローランズ。クールとしかいいようのないジャズをベースにした音楽。観客を不意打ちする突発的なアクションと暴力・・・。すごいと思うけれど、なんだかとても疲れる。日常生活の中で隠微に行使される権力と悪意によって人の精神が追い詰められ、破綻していく姿を見せつけられるのは正直つらい。だから、これまで何となく避けてきたけれど、この際、見ておくことにした。以下、簡単に感想を。
アメリカの影
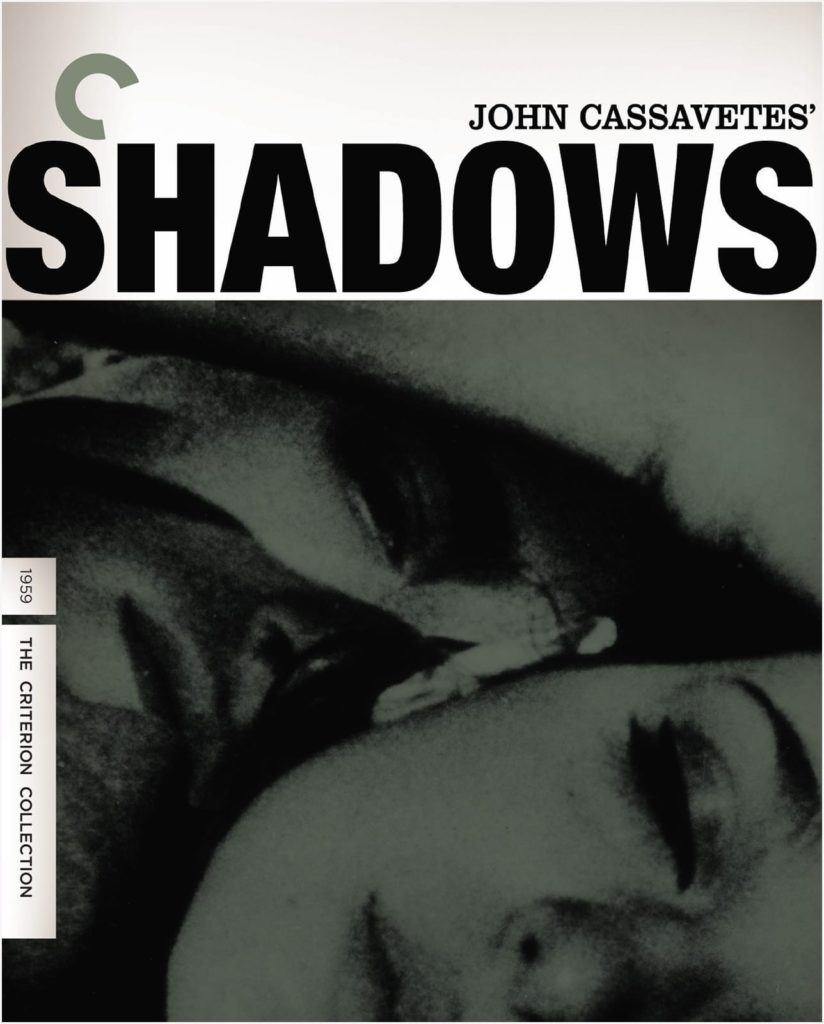
1959年に撮影されたカサヴェテスのデビュー作。ヴェネチア映画祭批評家賞受賞。ミュージシャンの黒人兄弟と、その妹で肌の色がそれほど黒くない美しい妹を巡る物語。彼女は社交的で文学や芸術を愛し、白人男性と恋に落ちる。しかし、彼女の部屋を訪れた彼は、黒い肌の兄弟2人を見てたじろぐ。上の兄は、そんな彼を見て白人に用はないと言って彼を追い出し、代わりに彼女を崇拝する黒人の若者を彼女にあてがおうとする。。。
こんな風に物語を要約しても、この映画の魅力は伝わらない。プロのジャズ・シンガーとして活動しながらうだつが上がらない上の兄は、歌の代わりに司会をやれと言われて傷つく。弟は、ジャズ・トランペット奏者を目指しているが認められず、不良仲間と軟派や喧嘩に明け暮れ、兄に小遣いをせびる毎日。。。ニューヨークの下町の猥雑さと若者の生態がリアルに描かれる。さらに、肌の色をめぐる差別や、黒人コミュニティ内での男女の差別意識なども描かれていく。ハリウッド映画では決して描くことができないスタイルは衝撃的だったと思う。
印象的だったのは、観客で身動きが取れない程混雑したジャズ・バーの場面。本当に隙間ひとつないほど人であふれかえった空間を弟がたばこを吸いながら移動していく。炸裂するジャズ、アップで映し出される顔。なんだか見覚えがある場面だと思ったら、ジャック・ベッケル監督の「七月のランデブー」(1949年)に出てくるパーティー場面にオマージュを捧げたものだと気づいた。カサヴェテスのシネフィルぶりがうかがえる。
フェイシズ
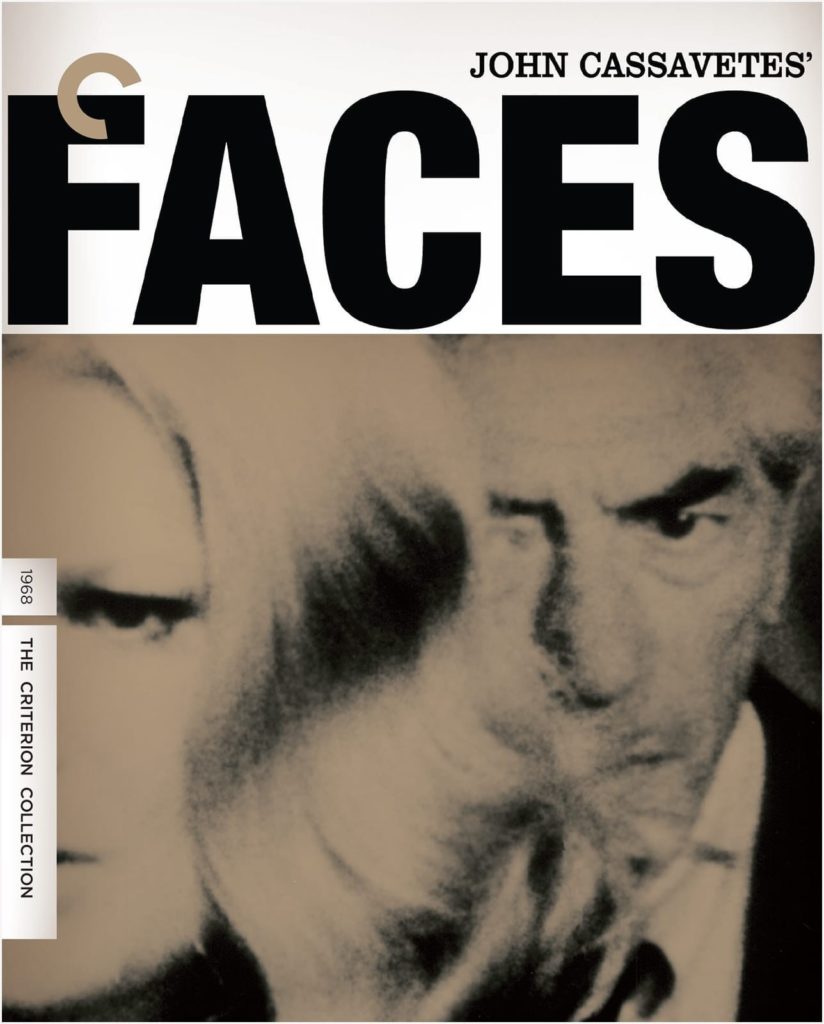
1968年の作品。ジーナ・ローランズが出演している。この作品はヴェネツィア映画祭で男優賞を受賞し、アカデミー賞にもノミネートされた。製作資金を捻出するために、カサヴェテスは自宅を抵当に入れ、撮影と編集も自宅で行われたとのこと。
物語は、一組の初老の夫婦を巡って展開する。二人は離婚の危機を迎えていた。夫は、偶然知り合った娼婦(=ジーナ・ローランズ)に心惹かれている。動揺を隠せない妻は、女友達と外で飲み歩く。そこで拾った若い男と共に、彼女らは自宅で飲み直すことにするが。。。
この映画でも、カサヴェテスの演出は鋭く人の精神をえぐっていく。例えば、夫がジーナ・ローランズの家を訪れる場面。彼女の部屋には既に先客がいて、気まずい空気が流れる。客は、地方からニューヨークにやってきたビジネスマンの2人組だった。そのなんとも言えない気まずさと、互いに相手の出方を見ながら時に威圧的に、時に卑屈に話を続けていく場面は、まるで演劇を見ているよう。若き日のジーナ・ローランズが、自堕落な生活を送りながらも毅然とした態度で男たちと接する娼婦を好演している。
こわれゆく女
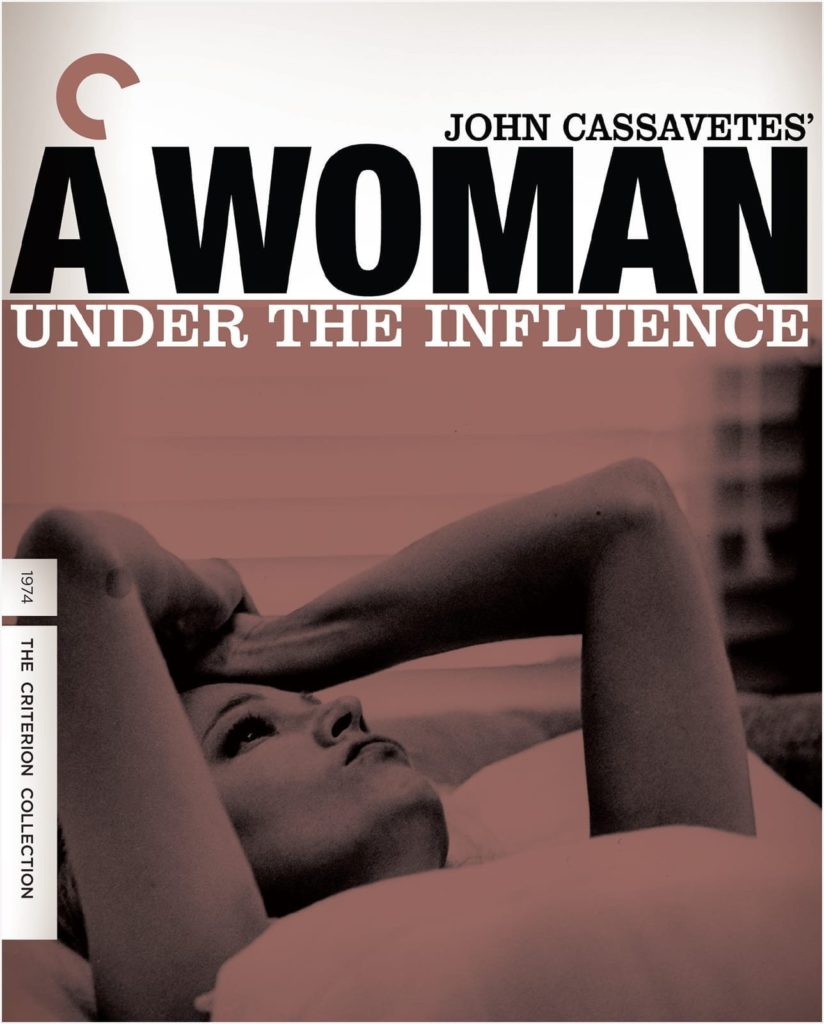
1974年の作品。ジーナ・ローランズとピーター・フォークが出演している。この映画で、ジーナ・ローランズはゴールデン・グローブ賞の主演女優賞を受賞した。
物語は、工事監督のニック(=ピーター・フォーク)とその妻メイベル(=ジーナ・ローランズ)を巡って展開する。夫妻には二人の息子とひとりの娘がいた。幸せな家庭を築いているように見える彼らだったが、メイベルは精神的な問題を抱えており、ニックが仕事の関係で帰宅が遅れるとひとり外出して見知らぬ男と飲んで酔い潰れるような生活を送っていた。メイベルは、徐々に精神に破綻を来していき、常軌を逸した行動を取るようになる。そして。。。
タイトル通り、ジーナ・ローランズが精神を破綻させていく姿をリアルに演じている。例えば、冒頭、子供たちを母親に預かってもらうために送り出す場面。母が乗っている車に子供たちの荷物を積み込み、子供たちを車に乗せるだけの場面なのに、うわずった声で子供たちに呼びかけ、神経質に忘れ物がないかと確認し、かと思うとくどくどと母親に子供たちの世話の念を押す姿から、不安定であやうい彼女の精神状態が浮かび上がる。すごい演技だと思う。
でも、この映画の怖さは、本当は彼女の不安定な精神を狂気へと追い詰めていく周りの人間の方にある。特に、ピーター・フォーク演ずるニック。工事監督として部下を率い、妻には優しい夫を演じているが、その言動にはどこか圧迫感がある。それに追い打ちをかけるニックの母親や隣人たち。この映画の原題は、「A Woman Under the Influence」(影響下にある女)で、実は主役はメイベルではなく、その周囲の人々にある。そのなんとも言えない人間関係の気持ち悪さを例によってカサヴェテスが濃密な演出で描いていく。見終わった後にずしりと人間の怖さを感じさせる作品。
チャイニーズ・ブッキーを殺した男
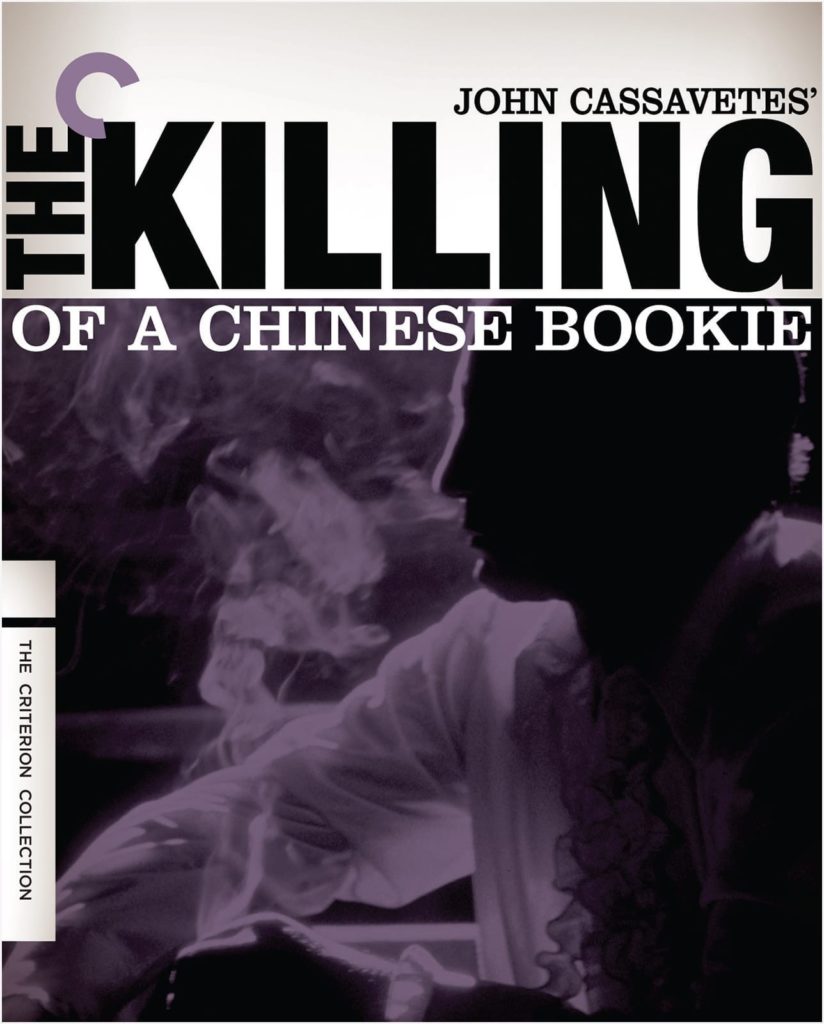
1976年の作品。ベン・ギャザラ主演。カサヴェテスがフィルム・ノワールに挑戦した作品。それまでの濃密な心理描写がいくぶん後退し、物語性がより前面に出ている。その意味では、他の作品に比べて見やすい。「グロリア」にも通じる作品だと言えるだろう。
物語は、ロサンゼルスでナイトクラブを経営するコズモを巡って展開する。彼は、フランスの有名なナイトクラブ「クレージー・ホース」になぞらえてクラブを「クレージー・ホース・ウェスト」と名付け、バーレスク形式のショーを上演している。役者と女たちを集め、自ら台本を書き、演出もしている彼だが、客たちはただのヌードショーしか期待していない、そんなナイトクラブである。ある時、コズモはギャンブルで大負けしてしまい、莫大な借金を背負う。借金の相手はイタリア・マフィアとつながりのある高利貸しで、彼らはコズモに、ある中国人の暗殺を持ちかける。それは、彼らと対立する中国人マフィアの首領だった。。。
もちろん、これだけの場面設定であってもカサヴェテスが「まともな」フィルム・ノワールを作るはずがない。まるで「オープニング・ナイト」を先取りするかのように、ショウの舞台裏で繰りひろげられる役者の不安や葛藤があり、コズモと客たちとのやりとりが挿入される。裸体をさらけ出す女たちにもそれぞれの人生と生活があり、コズモとの関わりがある。フィルム・ノワールとは言え、物語はなかなか「犯罪」へと向かわない。
とは言え、ターゲットとなる中国人の邸宅に侵入して用心棒をかいぐる場面のスリリングな演出は素晴らしい。あるいは、映画の最後、イタリア・マフィアとの無人のビルでの銃撃戦も見応えがある。まさにフィルム・ノワールとしかいいようのない、暗い闇の中での孤独な男たちの戦いが描かれていく。米国はカルト作品として評価されているとのことだけど、分かる気がする。
ということで、週末をまるまるつぶして4本、カサヴェテス作品を見たことになる。インディペンデント映画の雄にふさわしく、その作品は濃密で、実験的で、深く人間の心の闇をえぐり出す。そのクオリティの高さには圧倒されるけど、見ていると逃げ場がなくなるような気がしてくる。たぶん、育った映画環境と時代のせいかもしれないけど、同じインディペンデント映画であれば、僕はジョナス・メカスの日記映画の方を圧倒的に支持するし、あるいはカサヴェテスの次の時代のインディペンデント作家であるハル・ハートリーの方がいい。
とは言え、多分、まだ見ていない「ハズバンズ」が公開されたら駆けつけるんだろうな。。。なんだかんだ文句を言っても、やっぱりカサヴェテスの作品には抗しがたい魅力があるのも事実なのである。