梨木香歩著「冬虫夏草」
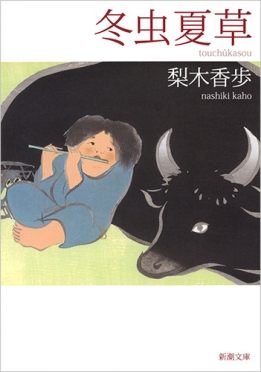
梨木香歩の「冬虫夏草」を読む。「家守綺譚」の続編。「家守綺譚」では、主人公の綿貫征四郎は基本的に自宅におり、そこに様々な人々や死んだはずの友、河童、犬、龍などが訪れるという体裁を取っていた。前編の基本的な世界観は踏襲しつつ、続編の「冬虫夏草」では、綿貫征四郎は自宅を離れて旅に出る。旅の目的は、失踪した愛犬ゴローの捜索、ともう一つはたまたま耳にした「イワナ夫婦が人間になって経営している宿」に泊まりたいという想い。大学時代の友人である植物学者の南川(モデルは南方熊楠?)の言葉に誘われるように、綿貫征四郎の鈴鹿の山に向けた旅が始まる。
前作同様、「冬虫夏草」でも様々な変化のものたちが現れる。河童の子供、赤龍の化身、南山で亡くなった娘の霊、ムジナ、カワウソ・・・。もちろん、前作の主要人物であった高堂も登場するし、ダリヤの君も健在である。梨木香歩の世界では、生きている人も死んでいる人も妖怪変化も神々とその使いも、ひとしなみにこの世界を往来し、あたり前のように姿形を刻々と変えながらこの世界での存在を刻んでいる。
綿貫征四郎の旅は、このような様々なモノたちとの出会いによってどんどん脇道にそれてゆき、道草を重ねていく。しかし、それが心地よい。旅とは本来、このように日常を離れて異界と触れる機会だったはずだ。目的地までの最短距離をただ移動するだけでは、それがどんなに風光明媚な場所や想像を絶する場所であったとしても旅ではない。ただの空間移動である。旅とは、ここではない場所と時間を経験し、ここにはいない他者と出会うための特別な時間である。この物語を読み進めながら、僕は旅の楽しみを思い出し、綿貫征四郎の旅が終わらないように、ただただこのように脇道にそれながらいつまでも続いていくようにと念じていた。それは、もしかしたら旅の楽しみであり、読書の楽しみであり、人生の楽しみなのかもしれない。そんなことをさりげなく提示してくれる梨木香歩さんの筆致が愛おしい。
その上に、梨木さんの筆は、綿貫征四郎の日常生活とこれを取り巻く自然を淡々と描きながら、生のありようと世界の本質についても考えさせてくれる。難しい哲学的な抽象概念をもてあそばなくても、人はこの日常の営みの中で、ただあたり前に思考しているだけで、世界の本質にたどり着くことが出来る。このことを、梨木さんはきちんと教えてくれる。
例えば、次のような文章。庭にモリアオガエルが産卵し、その卵がまさに孵化しようとした時に池にイモリが集結していることに綿貫征四郎が気づいた時の語りである。もちろん、イモリは卵から孵化して池に落下しようというモリアオガエルのオタマジャクシを食べるために集結しているのである。それは、生の残酷さを示しているかもしれないが、綿貫征四郎はさらにその奥に自然の摂理を感じとる。
そうか、と腑に落ちた。モリアオガエルのおたまじゃくしが、サルスベリの枝先の卵塊から池に落ちるのを待ち受けているのである。水面に落下する寸前を、取って食おうというのだ。モリアオガエルにとってはむごいことだ。この世に生まれ出た次の瞬間には暗黒の世界に戻されるのだから。だが、その可能性も考えてこのように無数の卵が産卵されるのであろうから、これも自然の摂理というものであろう。イモリもよくその孵化の気配を嗅ぎ取ってこうして集結したことだ。それに斯くも清らかな月光を総身に浴びつつ空中を落下する、その一瞬が一生のすべて、というのがモリアオガエルにとって、本当に不幸なことかどうかわからないではないか。
それは誰にもわからない。その一生の充実は、長さだけでは測れない。
月は皓皓と照っている。
梨木香歩「冬虫夏草」
美しい文章だと思う。その美しさは、こうした自然の一場面を的確に切り取っているだけでなく、その一瞬に世界の本質を描ききっているからだと思う。まるで禅画の世界のようでもある文章。ここに梨木香歩の文章の魅力がある。
そして、この本のテーマである「冬虫夏草」。冬虫夏草とは、冬場は虫として活動していたものが、夏になったら植物に変化するという漢方薬の原材料である。登場人物の南川の言葉を借りれば、「幼虫のうちに糸状菌の一種に感染し、菌糸が内部で増殖、ちょうどサナギになったときに体表を突き破って子実体が外へ現れるんだ。根っこの部分はサナギに繋がっている」という、蛾の幼虫が糸状菌に喰われたものを指す。これも自然の残酷な摂理のはずなのだが、綿貫征四郎は、そこに蛾の幼虫が昆虫界から植物界へと身を転じる異類婚を想像する。このように、生命とは特定の実体を持たずにただその形態を変えながら流転を繰り返しているのだと梨木さんは語りかける。
このテーマは、本書で繰り返し提示されるだろう。生の循環。生きているものも死んでいるものも、形を変えながら互いに呼び交わし合い、変転を繰り返しながら関係性を維持していく。これが世界のありようだと梨木さんはひっそりと語りかける。そして、ふとしたことからイワナの宿を継ぐことになった河童の子供にこんなことを語らせる。
ーーだが、イワナの宿に常駐するとなると、君の生活の仕方と折り合うのかね。夏と冬とではそれ、住む場所も生活の仕方も違うというではないか。
ーーなに、それは生物一般に云えることではないでしょうか。そのときどき、生きる形状が変わっていくのは仕方がないこと。それはこういう閉ざされた村里に住む人びとでも同じことです。人は与えられた条件の中で、自分の生を実現していくしかない。
ーー君は何か、宗教書か哲学書を読む習慣があるのかね。
ーーいえ、独自に達した境地です。
河童族とはかくも諦観を持って己の生き方を心得た種族なのか。
私はすっかり感じ入った。
このように語った後で、梨木香歩は、次のように続ける。そこには彼女の、世界に対する、自然に対する、人生に対する哲学が読み取れる。難しい抽象的な観念ではなく、具体的な自然のありようとそこに生きる人の生業から導き出された思想。根っこを持っているからこそ、その言葉は深く、しめやかに心にしみこんでくる。
夏と冬では生きる形が違う、それはサナギタケ、冬虫夏草を彷彿とさせた。南川は、あれはただ、菌が昆虫の身体を乗っ取っただけだ、というようなことをいっていたが、森羅万象、大きく見れば、そもそもはひとつのもの、周囲の条件によって、現れる形質、形状が違ってくるというように考えられるではないか。冬虫夏草はその象徴的なものとも思える。「同じ場所」を使っただけの話だ。とすれば河童がイワナのあとを継ぐくらい、如何程の不都合があり得よう。
こうしてこの長い物語はとりあえずの集結を迎える。綿貫征四郎は、愛犬ゴローと無事、再会できたのだろうか。荒れ狂う川を鎮める赤龍は、再び川に戻ることが出来るのだろうか。高堂が呟いた村々を沈める巨大な川桁はどうなるのだろうか・・・。物語は、様々な物語の種をそこら中にまき散らせながらいったん幕を閉じるだろう。この自然の摂理と同じように、物語もまた生々流転と変転を繰り返して死と再生を経ていくのだから。