梨木香歩著「ぐるりのこと」
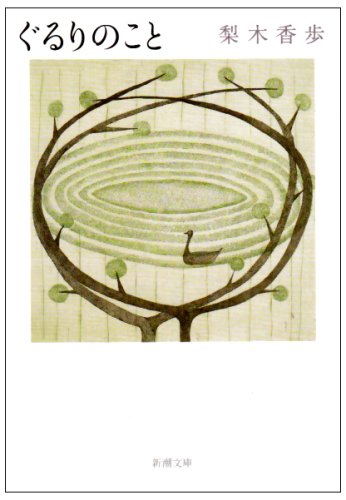
梨木香歩さんの「ぐるりのこと」を読む。2004年の作品。梨木さんが「沼地のある森を抜けて」という本を準備していた頃に、旅先で、あるいは日々の暮らしの中で、「ぐるりのこと」を綴った作品。
その思考は、執筆中の「沼地のある森を抜けて」に関連した発酵の話から、社会を騒がせた事件、隣人とのちょっとしたトラブルをめぐって広がっていき、時には英国留学時代の思い出が挿入される。中心的なテーマは、国や地域や民族や宗教によって作られた壁を乗り越えるコミュニケーションは可能か、そのような壁を乗り越えることが出来る物語をいかに生み出していくかということ。いつものように、梨木さんは、様々な記憶や出来事をたぐりながら、すぐに結論に飛びつかず、一つ一つ言葉をたぐり寄せるように思索を進めていく。その営みの誠実さに僕は深く心を動かされる。例えば、次のような一節。
もっと深く、ひたひたと考えたい。生きていて出会う、様々なことを、一つ一つ丁寧に味わいたい。味わいながら、考えの蔓を伸ばしてゆきたい。例えば、共感する、ことが、言葉に拠らない多様性に開かれてゆく方法について。最終的にはどうしても言葉で総括しなければならないのだけれど。何というアンヴィヴァレンツ。でも止められない。なぜなら、全て承知の上で、それでもなお私たちは、お互いを分かりたい、と欲して止まないものなのだから。それがどういう手段を選び、どういう馬鹿な結果を導こうとも。ああ。ああ。しょうがないなあ。
「共感する、ことが、言葉に拠らない多様性に開かれてゆく方法」。何という魅力的な言葉だろう。もしかしたら人間は生まれつきそういう能力を持って生まれてきたのかもしれないけれど、言葉を覚え、社会生活を営んでいく中で、そのような能力を失ってしまったのかもしれない。それが分かった上でも、なおわかり合おうと欲する気持ち。そんな両義性を生きるのが人間の本質だとすれば、あきらめずにそれを追求してゆこう。性急に結論を出すのではなく、蔓のように着実に広がりながら。。。梨木さんのこんな思考に僕は深く共感する。
あるいは、折り鶴をおることについて。広島の平和記念公園の式典用に準備された折り鶴が、ある時、悪意ある大学生によって燃やされてしまう。これを埋め合わせるために、同じ大学の学生が折り鶴を折り始めたと聞いて、梨木さんもこれに協力することにする。そして、次のように考える。
式典に間に合わせるための時間まで、まる一日もなかったので、どれだけ折れるか分からなかったが、とにかく手が黙々と動いてしまう。始めてすぐに、黙々と単純作業を繰り返す、これは、ほとんど意識を遠い次元に持って行く、メディテーションの一種のようなものだと感じた。抱えていた空しさも、悲しみも、ただ黙々と引き受けて、ひたすら違う次元の扉を開こうとする、祈りの力のようなものが、自分を動かしているように感じられた。原爆で犠牲になった人びとへの鎮魂、長崎の事件の被害者S君への思い、加害者の少年の魂のために、それから、折り鶴を焼いた若者に代表される社会の空気のために。それは、単に可哀想とか気の毒に、とかいうレベルではなく、何か全体の変容、別の次元への移行、彼らのために、そして彼らを包む、何かもっと大きい全体性のようなものへ開かれてゆく感覚だった。
(中略)少しずつ、少しずつやってゆけばいい。今まであった成分の喪われた大地なら、また、これまで考えられないような、全く違う方向からやってくる成分が加えられることも、充分考えられる。新しいそれが、従来の大地のバランスの中に収まって機能してゆくのには時間がかかるだろうし、眉をひそめるようなことも、しばしば起きるかもしれないけれど。
耐えられるだけ深く悲しんで、静かに自分の胸に収めていこう。そして少しずつ、少しずつ、土壌菌のように、自分の仕事を積み重ねて行こう。丁寧に、心を込めて。それがネムノキの花のように、儚く見えるものであっても。
折り鶴をおるという単調な作業が瞑想へ、そして祈りへと変わって行く。祈りにはこの世界が抱え込んだ大きな問題を解決する上ではたいした役に立たないかもしれないけれど、祈りがこの世に存在すると言うことの意味を深く考えていくことで世界は変わるかもしれない。そんな確信の強さが、梨木さんの仕事の魅力だと思う。
こうした思考を経て、梨木さんは「物語」に還ってゆく。なぜなら、物語を紡ぐことが、梨木さんの仕事だから。でも、それはただ物事を語ることではない。大きな課題を抱え込んだ現代に対峙する力を持った物語を紡ぐためには、自覚的な方法論が必要となる。それを、梨木さんは次のように説明する。
一個人が一個人であることを超えて、家系を、民族を、世界を語り出す。そのとき、例えばアイヌの古老の「個」はどうなっていたのだろう。その、たぶん、「個」と微妙に融合した「群れ意識」の在り方はもちろん、私たちが自らの所属すると思う「群れ」に対して感じるようなものとはまるで違ったものだっただろう。
近代化され、西洋化された現代の日本で、アイデンティティという言葉が使われるようになって久しいけれど、幾重にも取り囲む多層の世界、多様な価値観、それぞれとの間断なき相互作用、その中心にある不安定で動的な「自己」に、明確なアイデンティティを自覚するのは、生半可なことではないのだ、本当は。ましてやその「自己」が自身を取り囲む世界を語り出す、などということは。その中に棲まう、地霊・言霊の力とおぼしきものを総動員して、一筋の明晰性を辿りゆくこと、それが「物語化」するということなのだろう。
例えば、カラスが与えられた「自然条件」で生きてゆく、その命のくっきりと鮮やかな形を謳い上げること。歴史的な変遷を経てどんどんそのしつらえを変えていった「場」の中で、動かずにただただそこに存在する石が、自らの由来を誇らかに謳うこと。そういう、いくつもの世界が、様々な雲が無数に浮かぶ透き通った高い秋の空のように、クリアーに映えて見える、清かにも堂々とした明晰さ。
多様性を肯定しつつ、それぞれの命に即して明晰性をつかみ取ること。それが物語るということであれば、人間だけでなく、森羅万象、それぞれが自分たちの物語を語っているはずである。全体の複雑性を損なうことなく、焦点を当てられた細部を明らかにすること。単純化ではない、このような明晰性の在り方を探っていく中で、梨木さんは、個が与えられた条件と歴史の中でそれぞれの物語を語り始めるという壮大な世界観に到達する。今、現在の個の在り方をそのまま肯定しつつ、その個が存在するに至るまでの膨大な歴史の堆積を引き受け、さらにその個が属する全体性とも対峙する語り。それが、梨木さんの仕事なのである。だから、この短いエッセイの最後は、次のような決意表明で終わる。それは、ほとんど物語ることと生きることが同義になった新しい生の在り方を示しているのかもしれない。
物語を語りたい。
そこに人が存在する、その大地の由来を。