前田英樹著「小津安二郎の喜び」
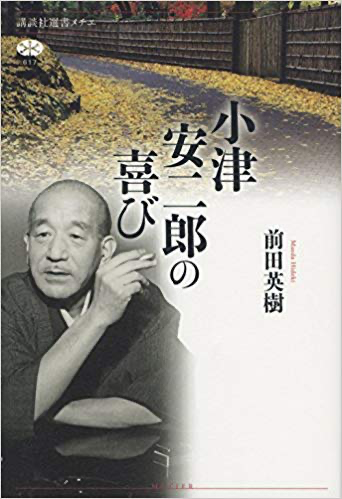
前田英樹の「小津安二郎の喜び」読了。彼が1996年に出した「映画=イマージュの秘蹟」を最近、ようやく読んでとても気に入ったので、2016年刊行の本書を購入。こちらも良い本だと思う。
前田英樹の出発点は、いうまでもなくドゥルーズの「シネマ」の枠組みにある。ドゥルーズによれば、世界は光に満ちている。これが「視える」ためには、ある種の縮減が必要である。人の場合、それは身体に対する有用性による縮減の形をとる。人にとって、世界とは、身体という中心を軸に、この身体が活動するための有用性という観点から縮減され、人に立ち現れるて「視える」ものである。これに対し、映画は極めて特異な縮減形態を取る。映画は、カメラによって撮影されるが、言うまでもなくカメラには身体がない。このような身体的中心を欠いたカメラが1秒間に24コマという形で世界を縮減させたものが映画である。人類は、映画を通じて初めて身体的な中心を欠いた世界を目にすることになる。
小津をめぐる前田の思索は、これが出発点になる。小津映画に固有の、無人の空間。それが固定ショットであれ、移動ショットであれ、小津映画には、誰が見ているのか定かでない無人のショットが度々挿入される。前田は、ここに神の視覚を見出す。身体的中心を欠いたカメラによる世界の縮減が露呈してしまう小津の無人ショットは、かくして神秘的な意味を帯びてくる。前田の言葉を引用しよう。
小津が撮る無人の室内ショットは、現実生活の行動が消え去った<永遠の現在>を捉えている。知覚機械としての映画キャメラは、そういうものを、いともあっさりと視てしまい、しかも、それを私たちの肉眼による視覚に入り込ませる。入り込ませ、私たちの視覚の態勢を根本から変えていくのである。
(中略)キャメラが引き出す視覚像は、物の充満を永遠の現在のなかに顕れさせ、物が在ることの神秘を啓示する。キャメラにはそのような働きがある。この場合、肯定的なものは物であり、光それ自体であり、運動する宇宙の開かれた全体である。
(中略)小津安二郎が、彼の映画の中に確固として打ち立てた方法は、キャメラによる視覚を、一貫して人間の視覚が含む潜在的方向に繋ぐものだった。キャメラの位置と画面サイズを限定し、それらを定型詩のように反復させるやり方は、そこに在るさまざまな物が、誰の視点からも観られてはいないこと、それらはそれ自体の持続によって、時間と記憶と静止と運動とを持つことを、根本から顕にさせた。水平のロー・ポジションと多層フレームとの固く端正な結合は、画面が持つ一定の拡がりを、それ自体として在る世界の奥行きに変え、画像を永遠の現在で満たした。
いくらでも引用を続けていきたいぐらい、本書の分析は刺激的である。小津映画を観るときに私たちが感じる畏怖の感覚。言葉にうまく言い表せないけれど、市井の人々の日常生活の描写から垣間見えるある種の神秘的な感覚が、前田の分析を通じて言語化される。これを読みついでいく時間は至福と言ってもいい。
ただ、本書の魅力は、そうした分析だけにあるのではない。ドゥルーズの枠組みを使った分析を、すでに前田は「小津安二郎の家:持続と浸透」と「映画=イマージュの秘蹟」で十分に展開している。本書で、前田が付け加えた新たな視点は、小津の映画がそのような形式的な分析ではなく、このような形式を通じて小津が開示しようとした内容の方にある。再び、前田の言葉をそのまま引用しよう。
日常の平板な暮らしよりも、事件とか、特殊な物語とかを好むのは、人間の中にある抜き去りがたい性癖である。いや、性癖というよりも、それは一種の本能なのだろう。(中略)私たちの関心は、絶えずそうした異変の方に向いていて、そこからこぼれ落ちてゆくものには注意を向けない。だが、私たちの命の本体は、そうやってこぼれ落ちてゆくものの無限の堆積の中にある。そのような本体に、ふと、じかに触れる時の強い喜びは、まさにそれが命の本体であることの明確な証ではないのか。
言い換えれば、小津の映画が、黙ってそれを観続ける者にもたらす喜びは、それが、私たちの命の本体をめぐる多様にして確固とした啓示であることから来る。(中略)彼は、異変の方にではなく、誰の耳目も引かない命の連続そのものの側に、その知覚がもたらす強い喜びの側に、いつも立とうとする。その理由の半分は、もって生まれた彼の天分にあるだろう。もう半分は、映画というものが、そうした知覚を、実にあっさりと、根本から可能にしてしまうものだというところにある。
私が、これからこの本で書くことは、小津の天分と映画の本性とが、どれほど深い地点で結ばれているか、その結びつきによって創造された喜びは、一体私たちに何を啓示しているのか、という点に尽きる。
「小津安二郎の喜び」まえがきより
こうして、前田は、現在見ることができる全ての小津映画を丹念に辿りながら、「潜在的なもの、それ自体であるもの、一切を生み出しながら持続する<永遠の現在>」を見出そうとする。それは、植物が生を次世代に継承しながら静かに自存していく生のありようにも似た、日本人の信仰であり、家族であり、道徳だろう。小津が示唆する道徳を、前田は以下のように捉える。
それは、後から次々と来る命に黙って希望を託し、みずからは老いて去る、という道徳である。その希望は、言葉にはならない。だが、それこそが、どれくらい古くからあるか知れない人間の暮らしの秩序を支えてきたものだろう。その秩序は、小津にあっては生の植物的循環のうちに秘められたもの、さらには、米作りをして生きる民の信仰心を息づかせてきたものである。
いままで、小津の映画を巡って、膨大な論考がなされてきた。日本語だけでなく、全世界のあらゆる言語で小津についての考察が蓄積され、現在も更新されているはずである。しかし、このように、映画の本質に迫りながら、同時に小津を通じて日本社会の深層に深く根差した分析はなかったのではないだろうか。少なくとも、僕は本書のひとつひとつの分析に深く心を動かされた。映画をめぐる本は無数に存在するが、ここまで心に染み入る言葉が連ねられている本は稀だと思う。映画評論という枠を離れて読まれるべき名著である。