鷲田清一著「素手のふるまい−芸術で社会をひらく」
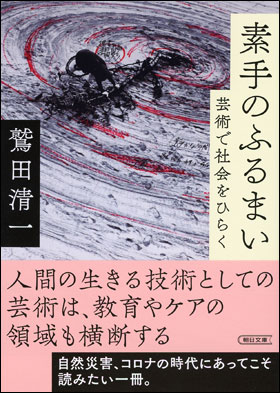
鷲田清一「素手のふるまい」を読む。東日本大震災後に、「アートと社会」をテーマに活動を続けるアーチストたちを取り上げて、アートのあり方を考えようという論考。取り上げられている作家は、小森はるか、瀬尾夏美、志賀理江子、川俣正など。
東日本大震災の被災地にそのまま住み着いて生活をしながら、徐々に映像作品を作り上げていった小森はるかと瀬尾夏美。同じく、被災地に入って写真館で活動しながら住民たちを巻き込む形で写真作品を制作する志賀理江子。国境を越えてサイト・スペシフィック・アートを展開し続ける川俣正。さらに、障害者や精神病者を対象にケアとアートを融合させようという様々なアーチストたち。それぞれ、従来のアートの枠を超えて社会に関わろうとする姿を分析しながら、アートの意味を改めて問い直そうという試みである。
現代社会は、様々な形でシステム化されており、自由が拘束されている。そのような社会は、個人に様々な役割を課し、その役割を通じた関係性でがんじがらめにされている。だから現代社会は生きづらい。特に、日本のような同調圧力の高い国では、こうした制約が個人に重くのしかかる。これを解消するためにはアートが必要である、と鷲田は言う。
わたし(たち)の存在を塞ぐもの、囲い込むもの、凝り固まらせるものへの抗いとしてこそ、アートはある。他者との関係、ひいては自己自身との関係をたえず開いておくために、そこにすきまをこじ開ける動性として、アートはある。とすれば、生を丸くまとめることへの抗いとして、アートはいつも世界への違和の感覚によって駆動されているはずである。そしてそれがまた、システムにぶら下がらなくても生きてゆける、そんな力の育成につながるはずである。そう、《生存の技法》に、である。
このように思考を進めていく中で、鷲田はレヴィナスの「根源的多様性」の思考へと至る。
一人として等しい個人はいない。その諸個人を一つの始原からともに捉えることを可能にするような特権的な平面は存在しない。自他の関係を俯瞰し、それを相互的なものとして取り扱おうとする第三者の視点は、自他を置き換え可能な、交換可能なものとみなす。が、それこそレヴィナスによれば「根源的不敬」とでも呼ぶべきものなのであって、人による人の「搾取」もそういう視点からなされてきた。だから、そういう第三項の周りに生じる集団性ではなくて、つまり同一の理念や価値やエートスを共有することで成り立つ集団性ではなくて、自他を包摂する第三者の不在と言うことを起点として思考を紡ぎ出さなければならない。他者との関係は、あいだに媒介となる共有のものが存在しないような位相でこそ出現するものだからだ。自他のこのような「絶対的な位相差」に定位した思考を、レヴィナスは私たちにもとめていた。
アートはおなじことを、おそらくはそれよりもっと手前で、もっと身体の活動に近いところで試みてきた。〈すきま〉をこじ開けるという仕方によってである。ここで言うところの〈弛み〉もこのことと深くかかわる。《根源的多様性》を指向するものは、それを指向するプロセスにおいてすでにその本質的な部分でそれをいくばくか実現していなければならない。
固定化し、個人を追い詰めてしまう社会を再活性化するために、他者性を導入しようとするアートが求められる。これが本書の主題だろう。アートにはそのような力がある。たぶん、それは人間という存在が、本質的に持つ表現への意思と密接に関わっているのだろう。美術館やギャラリーや映画館で展示される「作品」だけがアートではない。その視点はとても大事だと思う。鷲田さんの関心自体は、どちらかというと「社会」に向けられているような印象を持つけれど、彼の論考は、そのまま「アートとは何か」という問いにも向けられている。僕にとっては、そこがとても刺激的だった。