ナイト・シャマラン監督「シックス・センス」

M・ナイト・シャマラン監督の「シックス・センス」を観る。1999年の作品。ブルース・ウィリス、ハーレイ・ジョエル・オスメント他主演。アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞、助演男優賞、助演女優賞にノミネートされた。
公開からすでに20年が経っているから、ほとんどの人はあらすじを知っていると思うけれど、一応ネタバレ厳禁の作品なので、詳しい内容の説明は控えよう。舞台はアメリカのフィラデルフィア。市長にも表彰されたことがある小児科医マルコム・クロウ(=ブルース・ウィリス)が、問題を抱える少年コール・シアー(=ハーレイ・ジョエル・オスメント)のカウンセリングを引き受ける。実は、コールは幽霊を知覚することができるという得意な才能(=シックス・センス)を持っていたのだった。。。
シャマラン監督の作品の魅力は、映画史における新たな「恐怖」ジャンルを開拓したことにあると思う。但し、その「恐怖」はあまり怖くない。「シックス・センス」ではそれでもまだ少し怖いけれど、その後、作品が続いていくにつれて恐怖感はどんどん薄れていく。でも、やはりこれは恐怖映画のジャンルに入れるべきだろう。そうでなければ、スピリチャル映画というあらたなジャンルを作るしかない。いずれにせよ、彼がやろうとしていることは結構面白いと僕は思う。
映画史における「恐怖」とは何か。そもそも映画史は最も初期の作品から観客に「恐怖」感を起こさせるものだった。映画史でよく引用されるリュミエール兄弟の「ラ・シオタ駅への列車の到着」。映画創世記のわずか50秒間のサイレントフィルムだが、これを最初に見た観客はパニックに陥ったと映画史には記されている。ただ、列車が到着する場面を静止カメラで撮影しただけなのに、なぜ観客は恐怖におびえたのかというと、実物大の列車がスクリーン上でこちらに近づいてくるのを見て、映画に慣れていなかった観客が、本当に列車が近づいてくると勘違いしたということだ。映画というメディアと人間の初めての邂逅を巡る微笑ましいエピソードだが、ここには、映画と恐怖の関係を巡るある本質的な関係性が刻印されている。映画は、本来あるべきはずのないものがスクリーン上で動いているというだけの理由で、観客に恐怖を呼び覚ますことができる希有のメディアなのである。物語(説話、昔話、小説、詩・・・)では事情は異なる。聞き、読む者に恐怖を感じさせるためには、伏線が必要であり、現実世界における恐怖をベースにしなければならない。これに対し、映画はただそこに何かが映っていると言うだけで恐怖を感じさせることができる。
とはいえ、映画が発展するにつれて、観客は「ラ・シオタ駅への列車の到着」程度の映像などではパニックを起こさないように進化した。だから、映画は、観客に恐怖を感じさせるために「恐怖映画」というジャンルを確立し、様々な技法を発展させることになる。
一つは、まさに怖いものをスクリーン上に見せるという技法である。ドイツ表現主義映画(「ノスフェラトゥ」!)から、ユニバーサル・映画のモンスター達(「フランケンシュタイン」「魔神ドラキュラ」「狼男」「大アマゾンの半魚人」・・・)、さらにロメロが開拓した一連のゾンビ映画、エクソシスト・シリーズからジャパニーズ・ホラーの貞子に至るまで、映画的想像力は様々な奇怪なクリーチャーを生み出し、これをスクリーン上に提示することで、観客の恐怖を煽ってきた。
一方で、別の恐怖映画も存在する。できる限り、クリーチャーを登場させず、何者かの気配や不可思議な現象を連ねていくことで観客の想像力を刺激し、じわじわと恐怖感を高めていく一群の映画。それは例えば、1942年のRKO映画の名作「キャット・ピープル」であり、あるいはキューブリック監督の「シャイニング」だろう。ビジュアルな恐怖ではなく、気配の恐怖。これを可能にする無人の廊下や、どこからともなく聞こえてくるピアノの音、誰もいるはずのない部屋から聞こえる人声・・・。こうした技法を極限まで追求した作品が黒沢清監督の「回路」だと思う。あるいはこれに「Loft」、「叫」、「降霊」や「学校の怪談」シリーズを加えてもよい。ただ人が立っているだけの画面がもたらす恐怖。これもまた恐怖映画の一つのあり方である。
これ以外にも様々な技法がある。詳細については、もちろんこんなブログではとても説明できないので、参考書として「黒沢清の恐怖の映画史」と「映画はおそろしい」あたりを紹介しておこう。共に、映画における恐怖を巡る卓抜な思考が展開されているのでぜひ一度手に取ってほしい。
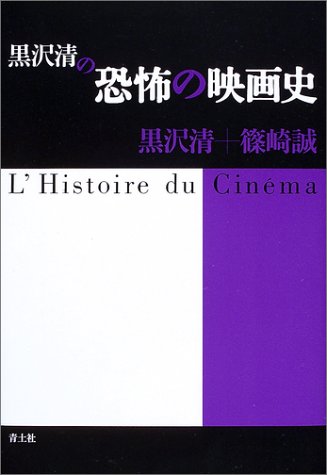
では、シャマラン監督の新しさはどこにあるのだろう。彼が提示するクリーチャーはそれほど怖くないし、また演出もそんなに恐怖を煽るものではない。正直、ほとんどの観客は彼の作品を恐怖映画としては見ていないのではないだろうか。でも、僕は、そこに彼の新しさを感じる。それは何かというと、もしかしたら、日常生活の中ですぐ隣にいる人が、本当は僕たちと決定的に異なる世界に生きているのではないかという恐怖である。
シックス・センスでは、それが「幽霊を知覚してしまう少年」という形で表現されていた。「サイン」では、宇宙人の襲来とかその予告とかが描かれているけれど、あの映画のテーマはまさに「サイン」、最愛の妻が瀕死の状況で主人公に告げた予言として登場する。ハプニングでは、ある時、植物が突然、人間を自殺に追いやる何らかの化学物質を放出し始める。「アンブレイカブル」「スプリット」「ミスター・ガラス」の三部作では、普通に日常を送っている隣人が実は超能力を持つ人々であり、そのことが世界に開示された時、人類自身が新たな進化の過程に入ることが示唆される。そう、シャマラン監督は、できる限り普通の状況にある神秘を描くことで、多くの人は気づいていないけれど実はこの世界は既に決定的な変容を遂げてしまっていると言う恐怖を表現しようとしているように見える。我々が普段、映画の中で見ている「恐怖」は、それがスクリーンの中にある限りにおいて隔離された恐怖である。しかし、シャマラン監督は、この隔離を解き放ち、映画館を出た後にもそれが持続するような不思議な感覚を映画に持ち込もうとする。それが怖い。
もちろん、21世紀の映像の氾濫に慣れきってしまった観客の目から見ると、そのような恐怖はただ退屈なだけかも知れない。映画はもっと刺激のある恐怖をいくらでも量産することができるし、観客は消費することができる。その意味で、シャマラン監督の作品には慎ましさすら感じる。
でも、例えば「シックス・センス」を見終わった後に、オリヴァー・サックスの「見てしまう人々:幻覚の脳科学」などを読み始めると、実は人間は様々なモノを見てしまう能力を持っているのであり、シャマラン監督が描く世界は、ダイレクトに現実世界と接続しているかも知れないという思いにとらわれてしまう。さらに超高齢社会に突入した日本では、認知症患者の多くがレピー小体型認知症を患い、様々なモノを幻視している事実に直面した時、この恐怖はじわりと私たちの体内に浸食してくるだろう。もしかしたらシャマラン監督の描く恐怖が、もっとも21世紀的な恐怖なのかも知れないのだ。