シモーヌ・ヴェイユ著「重力と恩寵」
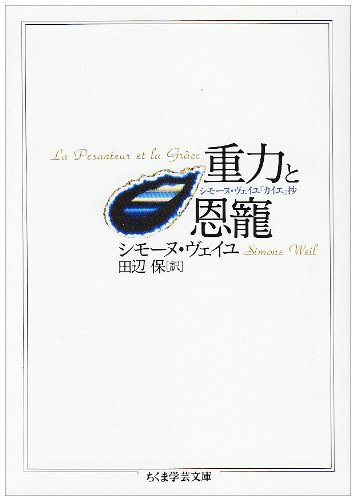
シモーヌ・ヴェイユの主著「重力と恩寵」を読む。以前のブログで紹介したように、彼女の「アンソロジー」を読んで心惹かれたので、ずっと気になっていた本を紐解く気になった。すごい。冒頭から引き込まれてしまい、気がついたら本に書き込みをしながら読みふけってしまった。本に書き込みをするなんて、学生時代以来。一文一文が深く、神秘的で心に染み入る。読書にもやはり出会いがあるのだろう。多分、学生時代に本書を読んでもほとんど理解できなかったのではないだろうか。
シモーヌ・ヴェイユは、ユダヤ人家庭に生まれた早熟の天才で、15歳で大学入学資格試験に合格、16歳で大学入学資格試験を通過し、哲学者アランの指導を受ける。19歳で高等師範学校に入学、その後高等中学校の哲学教師として教鞭を執る傍ら、労働運動に関わる。25歳の時、1年間休暇を取ってある工場で女子工員として労働。その際の思索は、後に工場日記となる。27歳でスペイン市民戦争に志願。しかし、炊事中に煮えたぎった油を足に浴びて負傷し除隊。その後、体調を崩して療養しつつ、時事問題に関する論考を次々と発表。28歳の時、聖フランチェスコの町アッシジに滞在し、カトリックに目覚める。結局彼女はユダヤ教からカトリックへの改宗は行わなかったが、生涯、カトリックとイエス・キリストへの深く透徹した想いと思索を維持した。32歳の時、難民救済事業に従事していたベラン神父と出会い深く霊的感化を受ける。彼に依頼して、フランスの田園地帯で農作業に従事しながら読書し、思索する日々を過ごす。この時のノートの抜粋が、「重力と恩寵」である。33歳で、ドイツのフランス占領を逃れてアメリカに亡命。しかし、フランスへの想いから逃れることができず、英国に移動。フランスのレジスタンス運動に参加するために運動するがかなえられなかった。フランスの子供たちが飢餓に苦しんでいることを知り、食事をほとんど取らない生活を送り衰弱。肺結核が進行してサナトリウムに移されるが、医師の説得にもかかわらず食物を拒否。結局、飢餓に等しい状態で34歳で没する。
激烈、としか言いようのない人生である。多分、そばにいたら大変だっただろうな、と思う。実際、彼女がこの「重力と恩寵」の元となるノートを執筆しつつ農作業にいそしんでいた間、彼女を世話していた農村哲学者ギュスターヴ・ティポンも、彼女と初めて会った印象を次のように語っている。
最初の頃の私たちの関係は、親しみにはみちていたが、努力を要するものだった。具体的な面では、はじめのうちわたしたちはほとんど何ごとについても一致しなかった。彼女は、かたい一様な声で、果てしもなく議論をつづけ、終わりというもののないこういう話し合いから抜け出してくると、私は文字どおりにくたくたになった。そのころ、わたしはこんな彼女に圧倒されまいとして、忍耐力とお愛想とで武装してあたった。。。。
ギュスターヴ・ティポン「解題」より
たぶん、彼女は絶えず議論し、状況にお構いなく自説を展開し、納得できなければ絶対に自分の意見を引っ込めない、そういうタイプの人間だったのだろう。しかも、思い込んだら、即座に行動に移すタイプ。本当に大変そうだ。
現実のヴェイユは、絶え間ない偏頭痛に苦しめられ、けがや病気で体調がすぐれない中で、憑かれたように書き続け、そして労働運動や市民運動に身を投じる人だった。さらに、工場や農村での肉体労働を進んで引き受けようとした。彼女の生きかたを知り、「重力と恩寵」の言葉を辿っていくと、どうしてこの人は、ここまで徹底的に自己を否定しようとするのだろうという疑問に捕らわれてしまう。彼女の中では、「神」と「被造物」がすべてであり、その仲介的存在としての「私」は消滅することによってしか、神の栄光を証することができない。そんな特異な思考が彼女の文章に頻出する。例えば、次のような言葉。
わたしが見たり、聞いたり、吸いこんだり、触れたり、食ったりするすべてのもの、わたしが出あうすべての人、わたしはそれらのものや人が神と触れ合うのをさまたげ、また、わたしの中で何かしら〈わたし〉と言いつづけるものがあるかぎりは、神がそれらのものや人と触れあうのをさまたげている。
わたしにも、それらのものや人、また神のために、つくせることがないではない。それは、自分の身を引くこと、それらのものや人と神との密な出あいにたちいらないことである。
(中略)
ただ、このわたしが姿を消してしまえるならば、神と、今わたしが歩んでいる大地、今わたしの耳に波音をひびかせている海・・・などとのあいだに、完全な愛のつながりが生じるだろう。
わたしの中にあるエネルギーだとか、天分だとかが、いったいどれほど大切なものなのだろう。そんなものにはつねづねうんざりしているから、わたしは消え去るのだ。
「消え去ること」
ヴェイユは、ギリシア哲学に精通し、ユダヤ教やキリスト教の文献を読みあさり、さらに古代インド哲学の「バガヴァット・ギーター」に親しみ、仏教思想に学んだ。キリスト教では、中世の神秘思想家で仏教との深い関連性が指摘されるマイスター・エックハルトの思想に影響を受けた。エックハルトや仏教思想は、徹底的に「わたし」を解体し、消滅させることを目指す。その自己否定の果てに、ある超越的な何かとの合一を達成しようとする。その考え方は、彼女の文章にも色濃く表れている。しかし、彼女の文章を読んでいると、単なる思想や宗教的実践の枠に留まらない、何か自己を完全に否定し尽くそうとする衝動を感じる。通俗的に言えば「破滅型」としか言いようのない生きかた。たぶん、彼女の思考の中では膨大なエネルギーが渦巻いており、それは彼女の身体的な制約などとは無関係に、彼女を追い立てていったのだろうという気がする。普通の人は、そんな状態に耐えることはできないけれど、彼女は不幸にしてそのまま行動に突っ走ってしまうことができてしまった。
そんな人生は、苦しみ以外の何物でもないのではないか、と言う想いに捕らわれる。実際、彼女は、繰り返し、苦しみについて、不幸について語っている。ただ、彼女は苦しみを否定しない。むしろ、それを積極的に肯定しようとする。
つらく苦しいことを受け入れること。受け入れたことがつらさにはね返って、つらさを減らすというのではいけない。そうでないと、受け入れると言うことの力と純粋さが、それに応じて減ってしまう。というのも、受け入れの目的は、つらく苦しいことをつらく苦しいこととして受け取るのであって、それ以外のことではない。
(中略)
キリスト教の何よりも偉大な点は、苦しみに対して超自然的な癒やしを求めようとせず、むしろ苦しみを超自然的に活かす道を求めているところににある。
できるかぎり不幸を避けようとつとめなければならない。自分の出会う不幸が、完全に純粋で、完全につらく苦しいものであるために。
「不幸」より
たしかに、ここには仏教的な思考が感じられる。仏教もまた、この世は苦しみに満ちており(四苦八苦)、これを認識することで執着を離れ悟りに至ることを説く(四聖諦・八正道)。でも仏教は、「だから苦しみを求めよ」とは説かない。そこが、ヴェイユの思想の特異な点だろう。
最終的に、ヴェイユはどこに救いを見いだしたのだろうか。例えば、以下のような文章に出会うと、彼女は、古代インド哲学が説く、アートマンとブラフマンの一致に理想を見いだしていたようにも見える。
わたしたちは、全体の一部分であり、全体にならわねばならぬものである。
アートマン。どうか人間のたましいが、全宇宙をからだとみるまでになるように。(中略)たましいは、今持つからだの外に出て、ほかのものの中へと移り動く。とすれば、全宇宙の中へと移り動いていくように。
宇宙そのものと同一化すること。宇宙よりも小さなものはすべて、苦しみのもとに服している。
わたしが死んだところで何もならない。宇宙はつづいていく。わたしが宇宙と別ものならば、そんなことがなんの慰めになろうか。だが、宇宙がわたしのたましいにとって、もう一つのからだみたいなものだとしたら、わたしの死は、わたしにとって、見知らぬ他人が死ぬのとそうかわらず、重要でもなんでもなくなる。わたしの苦しみにしても、同じだ。
(中略)
肉体の生命のリズムを、世界のリズムとつながり合わせること。このつながりをふだんに感じ、また、物質がたえず入れかわって、人間がこの世界の中にひたされているさまを感じ取ること。
(中略)
わたしの苦しみの、なくそうとしてなくせいない根底である〈わたし〉、このなくそうとしてなくせいないもの。それを普遍的なものにすること。
「宇宙の意味」より。
これを読むかぎり、彼女はヨガまたは仏教の呼吸法と瞑想法を実践していたような印象を受ける。呼吸を通じて深い瞑想に入り、自我を離れて宇宙と一体化すること。それは東洋では普遍的に見られる実践である。彼女がどこまでこの実践を行っていたかは分からない。
ただ、最後の彼女の死に様を読んでいると、唐突に、中世から近世の日本各地で見られる即身成仏やミイラ仏を思い出す。高僧達が、飢饉や災害の平定と人々の救いを願い、生きながらに埋葬されて読経を続けて死に至るという究極の修行法である。その死体は、死後に掘り出され、ミイラ化されて人々の信仰の対象となる。そんな激烈な信仰の道をヴェイユもほぼ餓死同然の死を迎えることでたどったのではないか。だとすれば、肉体的にも精神的にも苦しみの多かった彼女の生は、もしかしたら祝福に包まれて終わったのかも知れない。
まだまだ引用し、論じたい部分がある気がするけれど、とりあえずここまでにしておこう。これからも、たぶん、折に触れてこの本に立ち返ることになるだろう、そんな予感がする読書体験だった。