鈴木大拙著「神秘主義ーキリスト教と仏教」
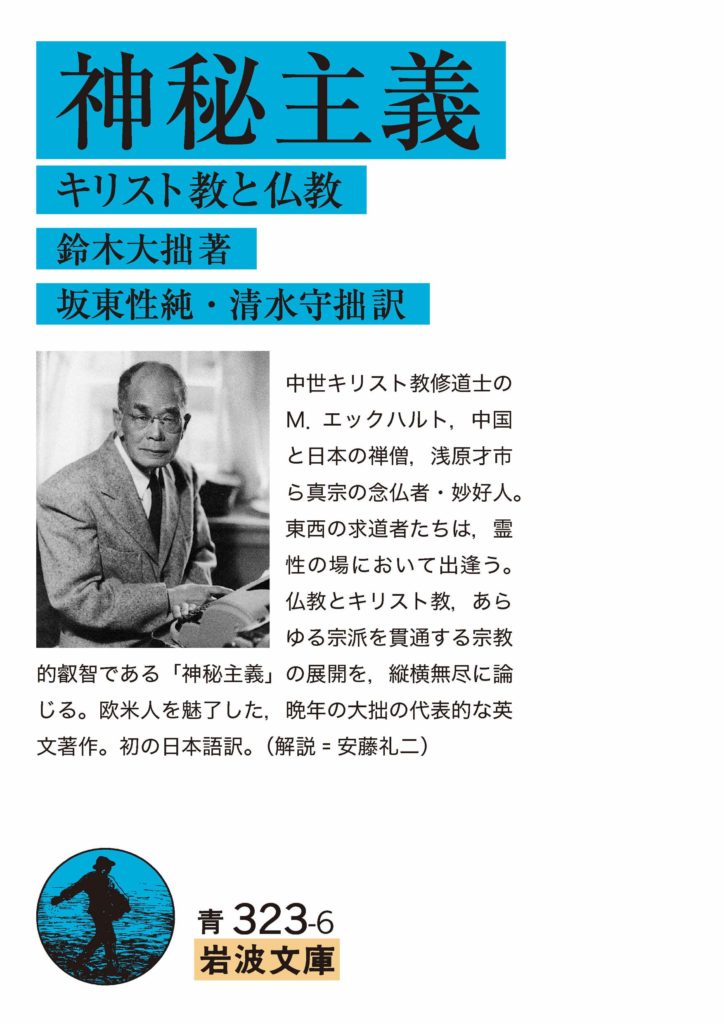
鈴木大拙著「神秘主義:キリスト教と仏教」が岩波文庫から出たので早速購入。解説は安藤礼二。まあ、2年前に大著「大拙」を刊行したばかりだから、安藤さんが解説を書くのは穏当な選択だと思います。20世紀初頭の神秘主義者の関係に改めて脚光を当てた安藤さんの功績は大きいですよね。
実は、私は鈴木大拙の本に二度挫折しています。「日本的霊性」と「東洋的な見方」です。ともに、仏教に対する彼の理解があまりにも類型的に感じ、しかもオリエンタリズムを前面に押し出そうとするところが何となく気になって途中で放棄してしまいました。考えてみれば、大拙が仏教について学んだ頃から仏教研究は飛躍的に進展しているし、また僕自身が、個人的にチベット仏教や上座部系の仏教のテキストを読み継いできているので、大拙が学んだ頃の日本の仏教理解に違和感を感じるのは当然なんですよね。大拙は、当時の英語圏の仏教学者からもその仏教理解を批判されているので、僕の反応もあながち生理的なアレルギー反応だけとは言えないと思いますが、こんな風に僕と大拙との出会いは少し不幸でした。
付け加えると、安藤さんの「大拙」も僕は途中で放棄しました。これも、安藤さんの文献考証を経ない断定と、やたらとテンションの高い文体についていけなかったためです。すべてを「真如」に還元するのはいくら何でも乱暴すぎる議論で、もしかして「真如苑」から金が出ているのでは?なんて思い始めると読む気をなくしてしまいました。でもまあ、情報としては貴重だから、いつか時間が取れたら再挑戦したいとは思います。。。。
ということで、「神秘主義」です。これは、大拙の晩年の著作。1957年の出版ですから、既に大拙は87歳。80歳になって渡米し、ニューヨークで暮らしながら世界各地で講演を行い、また、スイスのマッジョーレ湖畔で毎年開催されていたエラノス会議へも定期的に参加していた頃です。しかも、この本のオリジナルテキストは英語。大拙が学んだ禅の教えを相対化し、世界の多様な宗教や思想と対話を深めた上で晩年にたどり着いた彼の思索の到達点を知ることができる貴重な資料で、読み応えがありました。
この本はまずキリスト教神秘思想家のエックハルトの説教の分析から始まります。言うまでもなく、キリスト教徒でありながら、その教えの多くが仏教と共鳴し合っているとしばしば指摘されるエックハルトです。大拙は、エックハルトの言葉を引用し、これを分析しながら、エックハルトが繰り返し語る「無」、「無執着」、「離脱」に着目します。エックハルトは、一方で自身の中の神性を指摘しながら、神に至るためには自分を捨てることが必要だと説くのですが、そこに大拙は、仏教との共鳴を見いだします。
”純粋な(または絶対の)静けさとしての神の本体”あるいは”いかなる差別も入り込む隙のない、沈黙した砂漠”を、キリスト教徒はどのようなものと考えているのであろうか?エックハルトが神性の観念を”純粋なる無”として掲げる時、彼は仏教の空性の教えと完全に相応している。
神性の観念は、心理学を超えている。エックハルトは、その説教の中でしばしば、「魂の内にある創造されざる光」について言及し、「この光は、与えも受けもしない神的存在の、目立たず静止して動かぬ本質によって心満たされず、その本質がどこから来たのかを知りたがっている」と言う。
この「どこ」とは、「父なる神・子なる神・聖霊」が、まだ違いをはっきりさせる前の場所のことである。この本源に接触し、それが何であるかを知る、換言すれば、”私が生まれもしない時の私自身の顔を見る”ためには、私は”絶対の道の果てしなき空虚”の中に飛び込まなくてはならぬ。
鈴木大拙「マイスター・エックハルトと仏教」
刺激的な思考です。エックハルトの神秘的な説教を引用しつつ、これを禅宗の教え、道教の教え、さらにアンリ・マチスのアートなどを自在に引用しながら、超越的なものと邂逅する「空性」の場に接近させようと試みる。大拙の盟友である西田幾太郎の「絶対矛盾的自己同一」や「場所の論理」にも呼応する思考が展開されていきます。読み進めていくと、この世界を超えた超越的なものに接近しようという思考と実践は、ある点を超えればキリスト教も仏教も道教も(おそらくはイスラム教も)関係なく、同じルートをたどり始めるのだろうと実感できます。このような刺激的な思想家が近代日本に現れ、西田幾多郎や南方熊楠らと交流しつつ、スエーデン・ボルグからエックハルト、ジェイムズなどの西洋神秘思想を日本に紹介し、同時に日本の禅思想をジョン・ケージやサリンジャーなどの芸術家に伝えたという歴史的事実。まさに東西の思想の架け橋となった知の巨人であり、彼が日本の思想界に与えた影響は大きいと思います。
本書は、こうして、エックハルトの説教を手がかりに、西洋と東洋の違いを超えて共鳴し合う神秘的思考を探求していきます。そのプロセス自体も面白いのですが、結末にいたり、それはラディカルに変貌を遂げます。大拙は、旧約聖書の神の言葉「わたしは、有って有る者」を引きながら、これを真宗における「自然(じねん)」へとつなげ、さらに真宗の妙好人、才市の手記へと思考を展開していくのです。才市とは、市井の大工として生活しながら南無阿弥陀仏の名号を唱え続け、その思いを自由自在にノートに書き残した宗教者です。大拙は、才市の素朴な手記を楽しげに引用しつつ、そこに究極の信仰を見いだします。
親さまとは、すべての人々を摂取し、相手の身になりきった心のことであるが、この働きが、才市にその名「南無阿弥陀佛」を聞かしめ、まず、才市自身となるのである。これはエックハルトが、「神を義しい人びとの中に、また義しい人びとを神の中に生まれさせた」というのと全く同様で、親さまが自己を才市として個別化し、そうして己の名が才市として個別化した人によって称えられるのを聞くのである。阿弥陀はこうして才市という存在のうちで、「南無阿弥陀佛」(念仏)に身を変え、それと同時に才市は阿弥陀の御名を聞くことによって、阿弥陀となるのである。この南無阿弥陀佛(念仏)は、才市自身が称える声である。このような一体性においては、誰が阿弥陀で誰が才市なのかを区別することは難しい。一方を取り上げれば、必然的にもう一方も付随してくる。こうなると阿弥陀の浄土は才市の暮らしている娑婆世界以外の何ものでもないことになる。この娑婆というのは具体的な存在からなる世界のことである。
鈴木大拙 「蓮如の『御文(章)』
超越的なものを希求しつつ自己を無にすることによって超越者と一体化する至福の境地。この境地に達した者がいる世界では、娑婆自身が浄土に変容する。徹底した否定の先に見いだされる絶対的な肯定の世界。それは、大拙が長い精神的遍歴を経て到達した境地だったのでしょうか。世界を無条件に肯定したいなと感じた時に、何度でも立ち返って再読したい名著と出会うことができたような気がします。