フリッツ・ラング監督「西部魂」
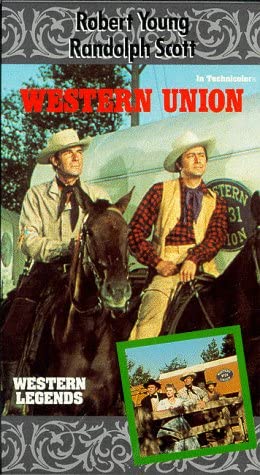
BSシネマで放映されたフリッツ・ラング監督「西部魂」を観る。1941年の作品。出演は、ロバート・ヤング、ランドルフ・スコット、ディーン・ジャガー、ヴァージニア・ギルモア他。ランドルフ・スコットが、この映画でも善と悪の間で揺れ動く複雑な役柄で魅せる。
フリッツ・ラング監督と言えば、メトロ・ポリスとドクトル・マブゼ・シリーズ、そしてフィルム・ノワールやスリラー、スパイもののイメージが強くて、西部劇のイメージが湧かない。だからこの作品はフリッツ・ラング監督の数少ない西部劇として貴重である。実際、この作品は、ラング的な明晰さに溢れた、観客の期待を心地よく裏切る名作に仕上がっている。
映画の舞台は、西部開拓時代のアメリカ。物語は、ウェスタン・ユニオン電信会社による大陸横断通信網の敷設工事を軸に展開する。ウェスタン・ユニオンの敷設工事を指揮するエドワード・クレイトン(=ディーン・ジャガー)は、かつて測量の旅の途上、荒野で負傷し、あやうく命を落としかけたところを、通りがかったヴァンス・ショウ(=ランドルフ・スコット)に助けられる。ヴァンスはどこか曰くありげで、エドワードを人里近くまで運ぶと、人びとの目を避けるようにその場を後にする。エドワードは、町の人たちに発見され治療を受けるが、そこで彼はヴァンスが銀行強盗の犯人の1人として追われていることを知る。
数年後。傷も回復し、本格的に大陸横断通信網の敷設に取りかかるエドワード。大勢の男たちを率いて工事を開始するが、男たちの中にヴァンスの姿を見つける。エドワードに気づいて慌てて工事現場から立ち去ろうとするヴァンスを、何も知らなかったかのようにエドワードは引き留める。そんなヴァンスに密かにクレイトンの妹スー(=ヴァージニア・ギルモア)は心を寄せる。そこに、ボストンで大学を卒業後、父親の命令で工事に加わることになったキザな若者リチャード・ブレイク(=ロバート・ヤング)が加わり、彼もまたスーに一目惚れする。一行が西に進むにつれて、ネイティブ・アメリカンの襲撃やヴァンスのかつての犯罪仲間による妨害工作が始まり、工事は重大な困難に直面する・・・。
フリッツ・ラング監督の独特の手触りが感じられる作品である。そもそも、冒頭からユニークである。この映画は、なんとバッファローとヴァンスの視線の切り返しから始まるのだ。カメラをじっと見つめるバッファローを捕らえたショットの後に、切り返しショットとしてヴァンスがカメラを見つめる姿が映し出される。バッファローと人間が見つめ合うという奇妙なショット。その違和感を打ち破るように、遠くから馬に乗った一群の男たちが砂埃をあげてこちらに向かってくる姿が遠景で映し出される。それに気づいたヴァンスは、ためらわずにバッファローの群れに突っ込んでいき、彼らに紛れて追っ手から逃れる。多分、普通の西部劇であれば、遠景から入って状況を説明してからヴァンスを映し出すはずだろう。それを省略してバッファローと人間との切り返しショットから映画を開始するところにフリッツ・ラング監督の才気を感じる。
(余談だけど、正面から見つめある二つの瞳の切り返しショットは、映画の中盤にヴァンスとスーの間で再現される。そのショットのリズム感が、ヴァンスとバッファローの切り返しにそっくりなところになんとも言えないフリッツ・ラング監督のユーモアを感じるのは僕だけだろうか。。。)
画面設計も素晴らしい。町中に溢れる色彩と看板の文字。西部劇の見慣れた風景のはずなのに、原色に塗られた壁や存在感を際立たせる文字の氾濫によって、今まで見たことのないような感覚に襲われる。しかも、その町には電信柱が立っているのだ!さすがはフリッツ・ラング監督。ただ西部劇を撮るのではなく、そこに時代の大きな転換を盛りこもうとする。その視点が斬新である。ゴダールが、「軽蔑」にフリッツ・ラングを招き、映画のことなど理解していないプロデューサーのことなど構わず黙々と自分のやりたいように映画を撮り続ける監督(まさにアメリカ時代のご本人!)を演じてもらったことがよくわかる。「西部魂」の町の風景は、まるでゴダールが描いた明るく、そこかしかに映画ポスターが貼られた南仏の風景を先取りしているかのようだ。
その後、映画は、スーを巡るヴァンスとリチャードとの恋の鞘当て、エドワードとヴァンスの友情、かつての犯罪仲間との絆とエドワードとの友情の間で苦悩するヴァンス、ネイティブ・アメリカンとの交渉、妨害工作の背後に垣間見える南軍の影などが手際よく語られていく。この語りの円滑さがフリッツ・ラング監督の真骨頂。この後に撮られる「マン・ハント」、「死刑執行人もまた死す」、「恐怖症」、「外套と短剣」などの傑作と並べても遜色がないくらいに、様々なエピソードが手際よく提示され、しかも互いに複雑に絡み合う。もちろん、そこにはユーモアもあれば、西部劇に特有の荒くれ男たちの交歓もある。ただただため息が出るぐらいの聡明さ。
もちろん、ラング監督の作品だから、すべてが透明な青空の下で進行するわけではない。光りと肯定の世界の後には、闇と否定の世界が訪れる。映画は、夜空の下で巨大な火柱が立ち上がり、人びとが火にまかれて逃げ惑う悲惨な光景や、血みどろの死闘もしっかりと描いていく。やはりラング監督は、1人の人間の内面における善と悪の葛藤というテーマから逃れられないようだ。「真人間」でも取り上げられた過去の犯罪仲間たちの誘いという主題が、この映画でも繰り返される。この内面の相克をランドルフ・スコットが説得力ある演技で提示する。良くできた映画だと思う。
アメリカ時代のフリッツ・ラング監督は、雇われ監督としてジャンル映画を撮り続けたけれど、一つ一つの作品には、ジャンル映画の紋切り型を解体し、新たな映像表現を立ち上げようという強烈な意思を感じる。これを商業映画という枠内で維持し続けたフリッツ・ラング監督。やはり偉大な映像作家だと思う。