大森荘蔵+坂本龍一「音を観る、時を聴く:哲学講義」
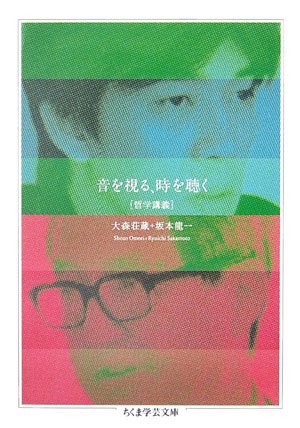
大森荘蔵さんと坂本龍一さんの対談をまとめた本。1982年に出版された書物の文庫化。なんというか、あの時代の空気感が甦るような懐かしさを感じる内容だった。
もちろん、日本の哲学者を代表する一人である大森荘蔵さんが、知覚や世界や時間や自己について語り、坂本龍一さんが良き聴き手として質問をし、さらに大森荘蔵さんの独特の思考に誘発されるかのように自身の作曲活動を顧みるという、とても知的刺激に満ちた対話である。YMOが大成功し、ワールドツアーを敢行した後に1年間活動を休止した時だったからこそ、こういう企画が成立したのだろう。
日本の哲学の最前線を走る哲学者と、世界中に大旋風を巻き起こしたテクノ・ポップのアーチストが、とがった哲学的対話を行い、それが本になった時代。内容を読者に分かってもらおうとか読みやすくしようという妥協は全くなされず、タイトルもぶっきらぼうに「音を視る、時を聴く」である。間違っても「3時間で分かる・・・」とか、「ビジネスマンの教養のための・・・」なんていう読者にこびたタイトルはつけない。そういう精神的な豊かさと出版社の心意気を、読者もちょっと背伸びして肯定的に受け入れた時代だからこそ可能になった本だと思う。それが懐かしさの理由である。
僕は不勉強で、大森荘蔵さんの著作はまともに読んだことがない。当時の普通の大学生と同じく、僕もニュー・アカデミズムに踊らされ、構造主義やポスト構造主義の本を読みあさった。そういう人間にとって、大森さんは少し旧いし、あまりにも象牙の塔の研究者に見えたのかもしれない。今回、初めて大森哲学に触れて、いちいち共感するところが多かった。こんなことなら、もっと早く大森さんの本を読んでおけば良かったと後悔することしきりである。
この本の論点は多岐にわたるのでとても簡単に要約することなどできない。ただ、大森さんが出発点とする「只今」という独特の時間論が、「私」という枠組みを解体し、音楽を演奏したり聴いたりすることが実はとても不思議なことだという形で展開していくところはとてもスリリングだった。
大森さんの議論は、ベルグソンの「純粋持続」という概念をベースにしている。今という時間は、時間の流れを瞬間的に切断した「刹那」ではなく、ある「持続」を持っており、それは「イマージュ」につながるという議論である。この考え方を音楽に適用すると、実は不思議なことが分かる。音楽を合奏している人たちは、合奏者の音楽を耳で聞き、それに「あわせて」演奏しているというのが日常的な理解だけど、厳密に考えると合奏者の音が自分の耳に達し、それを音として脳が認識し、それにあわせて自分で楽器を演奏して音を出すという一連のプロセスで「時差」が発生するはずなのである。であるにもかかわらず、合奏者は「同時」に音を出している。これは、刹那の集積として時間や自我を捉えている限り、決して解決することができない謎であり、「純粋持続」の導入が不可欠となる。
この問題を、例えば、坂本龍一さんは、シンセサイザーの作曲における千分の一秒や万分の一秒の音のずれがもたらす影響から考える。本来、人間には知覚できないはずのわずかなずれだが、それでもこうしたずれを意図的に音楽に組み込むことで、音の質感が変わってくる。ここでもやはり、人間はある時間と空間を一体として把握しているのである。では、生理的な知覚の限界と、自己の世界認識とはどこまで一致しているのだろうか。そもそも、音楽とは記憶と時間によって成立するアートであり、生理的な知覚に還元できないものだとすると、こうした音楽における知覚の時差を巡るパラドックスはどのように解消されるのだろうか。。。
刺激的な思考だと思う。こうした対話を通じて、大森さんは、例えば心の動きや知覚を大脳の活動に還元しようという現代科学のアプローチに異を唱える。世界は、何らかの物理的・生理的刺激やその意味の了解という形で思考してはならない。むしろ、音や言葉とともに立ち現れるのであり、人はその世界に立ち会うのだという独特の思考を提案する。とても印象的な言葉だったので、長くなるけれど引用しておこう。
・・・言葉は直接に何かを立ち現わせる。つまり、言い現わすのです。それと同様、たとえばごうごうという嵐の音は人の心にみみっちい情緒を呼びさますのではなく、あらあらしく揺れ動く野や林や街路を立ち現わすのではないでしょうか。心の情緒と言われるものはじつはこの荒れ狂う外部世界の相貌だと思うのです。嵐の音はその相貌をもった世界を鳴り現わすのです。音楽も同じで、荘厳なミサ曲を聴くと身がひきしまり沈痛な気持ちになるでしょう。しかしそれは「心の中」のことではなくて、その音楽が沈痛荘厳な相貌の世界を立ち現わすのだと思います。コンサートで瞑目して聴き入っている聴衆もそれぞれ自分の「心の中」に聴き入っているのではないと思います。その音が世界を響き渡って世界に沈痛な相貌を与え、その相貌を持った世界の立ち現れに面しているのだと思います。その曲はそういう相貌の世界を響き現わすのです。結局音は、言葉の音声であれ、風の唸りであれ、楽器の響きであれ、世界の中に鳴り、世界の中に籠もって、世界の相貌を変え、そしてその相貌の世界が立ち現れる、私はそう言いたい気がします。
言葉や音は、私の知覚を通じて了解され、意味を付与され、それが世界に投影されるのではない。言葉や音によって世界はある相貌を持った世界として、直接的に私に立ち現れてくるのだという発想。知覚や了解を介することの矛盾やパラドックスを突き詰めていくと、このような世界観にならざるを得ないのだという思考プロセスがスリリングである。大森さんは、こうした議論を進めていった上で、最終的に、時間についての奇妙な結論に達する。
ここで思い浮かべていただきたいのは、過ぎたことが思い出し様式で立ち現れているのも現在なんです。未来が立ち現れているのもいつでも現在なんですね。要するにわれわれの体験は、現在という場所をはずすことはできないわけですね。ですから、結局、へんな言葉ですが、過去と未来を含んだ四次元の世界の立ち現れが常時現れている。〈現在只今〉の中で知覚様式は中央にデンと据わっているんですね。そして裾野のように想起的な立ち現れと、つもりの立ち現れ、見込みの立ち現れに連なっているわけですね。そして、(中略)適切な言い方ではないですが、漸次、未来が現在化していくわけですね。
すべてを「現在只今」に収斂させようとする哲学。そこからはどんなアート論や自己論が展開されるのだろうか。大森哲学、もう少し探求したい気がしてきました。